
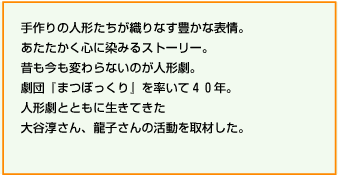
スッと照明が落ちる。 観客席が暗くなると、子どもたちの騒ぐ声に満たされていたホールが静まりかえる。 「始まるよ、ほら」と後ろの席でお母さんが幼い女の子に耳打ちする。司会者が舞台の端に現れ、演目の書かれた紙をめくる。『劇団まつぼっくり』の出番だ。 幕が開いて音楽が鳴る。みんなが知っている「おててつないで」の曲だ。 花を摘んでは おつむにさせば みんなかわいい うさぎになって はねておどれば くつがなる 晴れたお空に くつがなる 歌から姑まった人形劇『いちばん強いともだち』に観客の目は釘づけだ。目の前で芝居を演じるのは手作りの人形。昔ながらの素朴な人形劇は、CGを駆使した映画やゲームに慣れた目にはかえって新鮮に映る。大人は自分の子ども時代を思い出し、子どもは初めて見る舞台に興奮する。最初のうちはおとなしくしていてもそこは子どもたち、すぐに勝手に喋り出したり、席を移動しはじめたりするけれど、それでも人形劇を見たという記憶はずっと残るに違いない。そして、やがて大人になったとき、自分の親がそうであるように、自分もまた『まつぼっくり』の人形劇に自分の子どもを連れてやって来るのだろう。実際、この日、下妻市文化会館に集まった父兄のなかにはそういう人が少なくない。なにしろ『まつぼっくり』は、1966年の結成以来40年間も地元・茨城県下妻市を中心に活動をつづけてきた劇団なのだ。その活動は国にも評価され、代表の大谷浮さんは2004年には緑綬褒章を受章。今年4月に設立40周年を迎える。これだけの歴史を持つ劇団だけに、親子2代はおろか、3代に渡る観客だってけっして珍しくはないのである。「そういえば、この間の公演でもおばあちゃんに連れられて来た4歳くらいの女の子に会ったんですけどね。顔を見た瞬間にお母さんが誰だかわかった。何十年も前に会った女の子が、また子どもの姿で現れたという感じでしたね」 大谷さんとともに道を歩んできた妻の龍子さんが嬉しそうに語ってくれる。長くやっていると、こういう楽しみがあるのだ。 |
 劇団『まつぼっくり』(茨城県下妻市) 大谷 淳さん(82歳) 大谷龍子さん(74歳) |

上段:この日は、(左から)古谷野令子、浜名しげ子、江口正、大谷龍子、大谷淳、青木栄子、青木勇さんたち劇団仲間が熱演しました。
「そんなときですね。友達に誘われて小さな劇団に入ったのは…」
物も金も何もない時代だった。劇団の活動費を稼ごうと、小さな規模でできる人形劇を始めた。
「するとこれがおもしろかったんです。性分なのか、自分自身が舞台に立って演じるよりも幕の陰で人形を操るほうが楽しかったわけです」
本格的に人形劇をやろうと、友人たちとは離れて人形劇団『プーク』に入団した。ここであとから研究生として入団してきた龍子さんと知り合い結婚した。まさに人形劇が結びつけた縁だった。
『プーク』に在籍した9年間は全国行脚の日々。娯楽の少ない時代だっただけに、人形劇は各地で引っ張りだこだった。北海道から九州まで、大谷さんたち団員は腰の落ち着くことがなかった。団員が足りず、若手の龍子さんがいきなり『チルチルミチル』のチルチルの代役を振り当てられたりすることもあった。体力的にはきつかったが、充実した毎日だった。
その後も2人は『東京中央人形劇場』『太郎座』で活躍。テレビの人形劇などにも出演した。「ただ、子どもが生まれると仕事ばかりというわけにはいかない。しかも人形劇の場合は普通 の人以上に家を空けることが多いんですね」子どもとの生活をとるか、人形劇をとるか、大谷さんの選択は前者だった。
ちょうどそんなころ、下妻への引っ越し話が湧いた。龍子さんが戦争中に疎開していた下妻の教会が幼稚園をやっていて人手が不足している。手伝ってくれないか、という話だった。では、ということで大谷さん一家は東京から下妻へと居を変えた。1965年のことだった。ここで大谷さんは学習塾を経営。龍子さんは幼稚園に勤務。二人目の子どもも生まれ、家族がいつも一緒にいられる生活が始まった。

上演は、下妻だけでなく茨城県内の各所をまわっている。
「ああ、やっぱり人形劇はいいなって。そうだ、今度はボランティアで、できる範囲でやってみようかと2人して思ったわけです」
もともと嫌でやめたわけではない。その気になると動きは早かった。すぐに2人は『まつぼっくり』を結成した。
人形劇は1人でもできる芝居だ。しかし、やはり人数が多いほうが幅が広がる。二人が声をかけると、龍子さんの疎開中の学友たちが団員となってくれた。ほかにも学校の先生などが協力してくれ、劇団としての骨格ができあがった。
なかでも劇団に大きく貢献してくれたのが美術教師だった加藤日支勝さん。加藤さんはまだ脚本も備品も少ない『まつぼっくり』のために自ら脚本を書き、人形を何体も製作した。後輩の教師を誘っては劇団への参加を勧めた。それは地元・下妻に咲いた芸術の花に水や肥料を与えて大切に育てる作業にも似ていた。
「加藤先生のおかげで団員も増えたし、芝居のレパートリーも広がった。歴代の団員を数えると、この40年近くで加藤先生をはじめ50人近くはいるでしょう。『まつぼっくり』は小さな劇団ですが、大勢の人に支えられてここまで来られたんです」
団員は多いときで13人。現在は七人で活動している。稽古は週に1回。大谷家にある16畳の大部屋に集まっての稽古は真剣そのものだ。
「公演回数は年に5回前後ですね。そのたびに脚本や配役が変わったりするから、いつも新鮮な気持ちで臨んでいます」
上演場所は、下妻市の文化祭や、地域の学校、幼稚園、保育園などさまざま。下妻だけでなく茨城県内の各所をまわっている。
 手作り人形は場面ごとに表情の遣う人形が用意され、オリジナルの脚本で上演されました。
手作り人形は場面ごとに表情の遣う人形が用意され、オリジナルの脚本で上演されました。「多いときは客席が足りずに2回に分けて上演したものです。あのころは黒子姿で舞台の下にいても客席の熱気が伝わってきましたね」
観客が減ったのは少子化の影響も大きいが、いちばんの理由は娯楽が多様化したことにある。今の子どもは家にいてもアニメのDVDを見たり、ゲームなどで遊べる。楽しみが増えたから、わざわざ外に人形劇を見に行くことも減った。
「本当に、子どもたちはどこに行っちゃったんだろうと思いますね」
そう語る『まつぼっくり』の面々だが、その表情はけっして暗くない。不思議なことに、人数が多かろうが少なかろうが演じる側の意欲は「まったく変わらない」のだ。
「いつも精一杯やっています。たぶんみんな人形劇をやること自体が好きで、楽しくてたまらないんでしょうね」
手作りの人形は、見せてもらうと意外と大きい。顔のサイズなどは人間とはぼ同じだ。「顔は大きめのほうがよく見えるし、表情もつけやすいんですよ」
大谷さんが、この日2番目に上演した『嫁様の絵姿』に使った人形を手に持って操ってくれた。とばけた顔の人形が、角度によって笑ったり、寂しそうな顔になったりと表情を変えてゆく。人形を操るというのも、なかなか奥が深い。
普通の芝居と人形劇、演じる側の気持ちはどう違うのだろうか。
「やっぱり自分が動くのと人形を動かすのは違いますね。ただ、発声や表現は基本的に同じ。その人物になりきる、という点も共通 しています」
見ていると、ある部分人形劇の方が大変にも感じる。舞台の下に立って、腕だけで人形を操る。これはなかなかの重労働だ。
『嫁様の絵姿』は、美しいお嫁さんといつも一緒にいたいがために、野良仕事の間もお嫁さんが描いてくれた似顔絵をそばに置いておく太郎吉が主人公。やがて嫁のおさきちゃんは殿様に横恋慕され城に連れ去られてしまうのだが、意外な展開でハッピーエンドを迎える。民話をモチーフとしたオリジナルの脚本は、ほのぼのとしていて愉快だ。こうした脚本が『まつぽっくり』には40本ほどある。
手作りの人形は約100体。団員にとってはどれも子どものようなものだ。
「今年は40周年。それにふさわしいお芝居ができたらと思います」
がんばれ『まつぼっくり』!

民話をモチーフとした『嫁様の絵姿』の一場面。