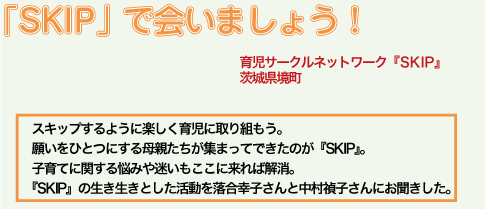
赤ちゃんが生まれた。それまではなにはさておき無事の出産を祈るばかりだったけれど、いざ産んでみればその気持ちはたちまち過去のものとなり、今度は育児で頭がいっぱいとなる。目の前にはこれなら妊娠中のほうが楽だったというくらいに大変な日々が待ち受けている。いや、すでにそれは始まっている。いろいろ覚悟はしていたものの、実際に赤ちゃんを抱く身となるとわからないことだらけで不安になる。誰か子育てについて相談する相手はいないか、疲れた心をほぐせる場所はないだろうか。これは世の母親ならば誰もが共通して持つ悩みだろう。 「そういう子育てで頑張っている若いお母さんたちに仲間や場を提供する。それがSKIP(スキップ)なんです」 こう語るのは、茨城県境町で子育て支援サークル『SKIP』の代表を務める落合幸子さんと副代表の中村禎子さんだ。 落合さん自身も8歳、6歳、2歳の3人の子を持つ母親。『SKIP』の活動を通じて子育ての仲間をつくってきたという。「正式な名称は『境町子育てネットワークSKIP』。もともと町には4つの育児サークルがあったのですが、それがひとつになって始まったのが『SKIP』でした」 発足は2002年の6月。きっかけとなったのは国の第三事業である社会福祉・医療事業団(子育て支援基金)からの誘いだった。 「そのころ私は『みのりクラブ』という子育てサークルに参加していたんですね。そこへ国から助成金を出そうという話がきたんです」 境町は埼玉県や千葉県との県境に位置する利根川流域の町だ。人口は約21,000人。利根川の水運で栄えた歴史のある町だが、鉄道や高速道路からは離れていて便は決して良くない。小さな町だけに乳児を抱えた母親が出入りできる場所も多くはない。そんな若い母親たちにとって育児サークルは頼もしい存在だった。 「町では、出産後、保健センターで子育て教室を開いてはいてくれるのですが、それは期間限定。私は県外の出身なので町に友達がいないし、『みのりクラブ』などの育児サークルがなければ子育ての話ができる仲間には出会えていなかったと思います」 同じように県外から嫁いで来て、育児サークル『なかよし』に参加していたのが2児の母である中村禎子さんだ。中村さんもまた育児の話ができる仲間を求めていた。 「『なかよし』の活動は毎月第1、第3木曜日の月2回。私にとっては本当に楽しみでした。子どもが風邪にかかったらどこの医院に行けばいいかとか、保育園や幼稚園はどこがいいとか、そういった実用的な情報が入ってくるのはもちろん、同じ境遇にある友達とお喋りができるだけでもずいぶんと息抜きになっていましたね」 当時、4つのサークルはどこも満杯状態。おやつや飲み物を持ち寄って話に花を咲かせる。絵本の読み聞かせをしたり、お絵描きをしたり、子どもたちを遊ばせながら母親同士も交流を深めていた。 そこに飛び込んで来たのが助成金の話だった。年間予算は、なにに使おうと自由だった。これを『みのりクラブ』だけで利用するのはもったいない。落合さんたちは『なかよし』など他のサークルの代表者に「一緒にやらないか」と声をかけた。そうして誕生したのがイベントを活動の中心に据えた『SKIP』だった。 ちなみに『SKIP』という名称は落合さんたち設立メンバーがつけた。 「そのときは3人のメンバーであれこれ考えたんです。そこで思いついたのがスキップでした。子育てはすごく大変。でも、スキップをするときに涙を流している人はいない。スキップをするように楽しく子育てをしようよ。そんな思いからこの名前に決めました」 |
 落合さん(左)、中村禎子さん(右)と子どもたち |

第2回は『劇団まつぼっくり』を招いての人形劇。第3回は母親同士のディスカッション大会と、これらも盛況のうちに終わった。こうして、年に数度のイベントを軸に『SKIP』の活動は広がっていくこととなった。
ただし、イベントを運営するスタッフの負担は相当なものでもあった。この種のイベントを開くには様々な事務的作業をこなしていかねばならない。使用する施設の予約やゲストの手配、参加者への告知や連絡、予算や参加費の会計等、ただですら子育てで忙しいのに落合さんの身にはこれらの仕事が集中して押し寄せて来た。
「夜は子どもを寝かしっけたら大好きな缶ビールを飲みながらポスターの挿絵を描いたり。楽しかったけれど、寝る間のない毎日でした」
結婚前は地方のテレビ局でカメラマンをしていた落合さん。体力はあったが、さすがにひとりでなにもかもをこなすのは無理があった。
「性格なんでしょうか。なんでも背負い込んじゃうタイブなんですよね」
見るに見かねて助っ人を買って出たのが中村さんだった。
「本当は『なかよし』の活動だけで十分満足していたんですけど、落合さんの頑張りを見て気持ちが動いたんですね。私もやってみるかと。落合さんをサポートして、この5年間ずっとスタッフの皆さんとともに活動してきました」
中村さんの加入によって、スタッフみんなが仕事を分担するようになった。イベントは回を重ね、これまでに「親子スイミングスクール」や「親子でのびのび体操教室」「家庭でできる親子遊びあれこれ」「メイク&ベビータッチケア教室」「親子遊び&ジャブジャブ池遊び」「グッドトイであそぼう」「親子でからだあそび」「つながりあそびうた」など様々なものを催してきた。設立2年目からは県や町から助成金が出て、その活動は広く茨城県内に知られるようになった。
最近の活動のなかでとくに人気が高いのが「子育て講演会」だ。これは東関東子育てサポートセンターの木村利行氏を講師に招いてのイベントで、毎回参加者から好評を得ている。木村氏は母親の子育ての悩みひとつひとつに的確にアドバイスを寄せてくれる。
なにもかもを自分たちで切り盛りする苦労はあったが、そこで解消されたものもあった。乳児を持つ母親の多くは孤立感を抱いている。子どもと一緒に家にいるだけでは気持ちが塞ぎがちになるし、自分だけが社会から取り残されてゆくのではないかという不安は拭えない。ことに第2子、第3子と連続して子どもが生まれた場合、母親は数年間は育児にかかりきりになってしまい、一種の浦島太郎のようになってしまいがちだ。『SKIP』の活動はそんな母親の生活を一変させた。
落合さんの場合、代表として設立に携わって感じたのは「昔の自分が戻って来たこと」だった。こうした活動をするからには夫や家族の協力が必要となる。『SKIP』設立の話を聞いて、夫から「お前はなにがしたいんだ?」と尋ねられた。そう訊かれて、あらためて自分はなにをしたいのだろうと考えたとき、導かれた答えは至極単純なものだった。
「自分は楽しみたいんだなって気が付いたんです。2年おきに子どもを産んでいたものだから、世の中と自分との間にだいぶ距離が生まれていた。子どもたちは可愛いけれど、自分自身ももう少し外に出て楽しみたいなと思ったんです」
そういう意味で育児サークルの活動は一石二鳥ともいえた。
「イベントに講師をお招きするのに電話で交渉をしたり、大勢の人と接しているうちに社会人として生き生きと仕事をしていたころの感覚が甦ってきたんです。なんだか何年間も宙に浮いていた自分が戻って来た感じで、これは嬉しい発見でした」
顔つきも変わったという。緊張感がいい意味で表情に生気を与えてくれた。むろん、こうした変化は落合さんだけのものではない。
中村さんは『SKIP』の活動を仕事のようなものだと考えている。
「子どもたちに今日は『SKIP』だからって言うと、お母さん仕事?つて訊かれるんですね。まわりにはそういうふうに映っているんでしょうね」
 (上)運営スタッフ(下)バザーはいい物がいっぱい
(上)運営スタッフ(下)バザーはいい物がいっぱい普通の主婦では味わえない体験もしている。活動を通して出会う育児や教育のスペシャリストや行政の人々との出会い。町長と話す機会もあった。数年前まで境町では老人介護には力を注いでいた反面、育児に対しては関心の薄い部分があった。だが、『SKIP』の活動がそんな町の行政に一石を投じた。現在では「女性が安心して子を産み育てられる境町」にしていこうと町がバックアップしてくれている。けっして大きくはない町にとって生まれてくる子どもたちは地元の将来を担うかけがえのない宝だ。こうした町の取り組みはいずれ少子化対策のひとつのモデルケースとして目に見える成果となって表れるはずだ。
今迄は毎回アンケートをとって参加者の希望をとり入れたいイベントを企画してきた。しかし、木村先生と出会って乳幼児期に大切なことは何かを改めて考えるようになった。その結果、ただ楽しいだけではなく「子どもにとって本当に大切なもの」を参加者に提供していくことを柱にしていこうと方向性が定まってきた。ビデオ、テレビに頼らない親子スキンシップのからだ遊び、ジュースや袋菓子ですませないで旬の地元野菜をおやつに替えて、そういった子育てが各家庭で実践されていく親子の輪、地元の輪を作っていくことを目標としてひとつひとつ前進している。
町内のさまざまなボランティアグループとの連携もそのひとつ。従来から更生保護女性会だけではなく食生活改善推進協議会や4Hクラブ、ライオンズクラブや青少年健全育成町民の会などのバックアップを得て町全体で子育てを応援していこうという風土が徐々に広まりつつある。
『SKIP』がある限り、これからもきっと親と子の笑演が絶えない境町でありつづけるはずだ。
(2007.10 掲載)