 |
 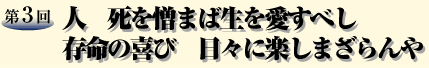 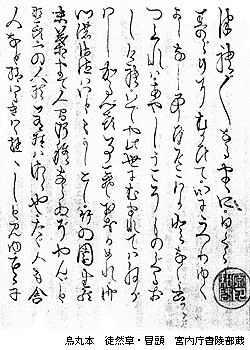 私たちの通
常の生活は、その日その日の目の前の仕事に追われながら、さまざまな出来事に遇っては喜怒哀楽をくりかえすようなことが多く、与えられた命とか、その日をいかに生くべきかについて真剣に考えることは、意外と少ないのではないでしょうか。 私たちの通
常の生活は、その日その日の目の前の仕事に追われながら、さまざまな出来事に遇っては喜怒哀楽をくりかえすようなことが多く、与えられた命とか、その日をいかに生くべきかについて真剣に考えることは、意外と少ないのではないでしょうか。このことについて、兼好法師は『徒然草』第九十三段に、たいへん興味深い話を載せています。話は、牛の売買契約が成立したものの、売約ずみの牛が、まだ代金が支払われないうちに急死してしまったことにかかわるものです。ところで、この場合、牛の買い手が得をして、売り主が損をしたと語る人に対して、兼好の意を代弁していると思われる「かたへなる者(そばにいる人)」が、
と言ったというのです。つまり、牛の売り主は一見するとたしかに損をしたようにみえますが、実は大きな利益を得ているのです。そのわけは、生命のあるということは、いつ死が到来するかわからないのです。ここでは、たまたまその死が牛に到来したということで、人間の場合も牛と同然なのです。思いがけず牛は死に、売り主はその死を免れたわけです。このことは、売り主は、鵞鳥の羽よりも軽い牛の売価に比して、「一日の命、万金よりも重し」という宝を得たことになるのだから、決して損をしたのではないというのです。まさに、生死無常の世界に生きる人間の生命を見つめたところより出ずる至言と言えましょう。 「かたへなる者」は、さらに続けます。
人間は死を恐れ、憎むものですが、そうであるならば、限りある生命(いのち)を愛すべきであり、いまここに生きていることの喜びを日ごとに楽しむことが切実に求められてきます。たいていの人間は、不可避の死の迫っていることに気がつかないので、死を恐れず、これを憎もうとしませんが、もし、死が刻々に身に迫っている実相に気がついたときには、死を恐れ、かつ憎むことになりましょう。その結果 、生を愛し、生を楽しむこととなり、また、「一日の命、万金よりも重し」という感動も生ずるというのです。しかし、この境地は、まだ死の恐怖が根底にあり、それから自由になってはいません。そこで、「生死の相にあづからず」という、生・死の相対世界を超えた絶対の境地を理想とする仏教的悟りが最終的に求められているのです。 私たちが、生命無常ということを本気で考えたとき、どのような生き方が求められてくるのでしょうか。このことを考えるに当たり、この第九十三段は極めて示唆的であり、また、混迷の現代を生きる私たちに一つの指針を与えてくれるのではないでしょうか。生死超越の境地にまではいたらなくても、生命の無常をいたずらに嘆き悲しむのではなく、万金よりも重い命を実感し、生を愛し、存命の喜びを日々に味わい楽しみながら生活していけたら、それこそ、どんなにかすばらしい日々となることでしょう。 |