 |

と述べます。自然界における四季の推移について、春が暮れて後に夏になり、夏の終わった後に秋が来るという、常識的な見方を否定し、春は春として進行しながら同時にそのうちに夏の気をもよおし、夏のうちから早くも秋の気を通
わし、秋は秋であるままにいつしか寒くなる、と観察しています。ここには、推移した季節という「果
」に対する、その「因」を考える、つまり物の変化を「因」と「果」の関係として考えるという因果
観に基づく思考がみられます。このようにして、変化の相の実態を鋭く見抜き、その変化の相をダイナミックな動態としてとらえるという、凡庸を脱した視点が提示されているのです。
と述べます。「木の葉の落つる」という現象を、「下より萌しつはるに堪へずして」<葉の下から芽生える力の勢いにこらえきれないで>起こる現象ととらえます。ここでは、落葉ということの因って来るところを、新芽の萌え出る力の蓄積・充満に堪えきれなくなることにみているわけです。つまり、落葉という消滅現象の由来を、新芽の萌え出る力という生成現象から説いているのです。“消滅”という変化の現象を“生成”という変化の現象からとらえ直しているわけです。従来、日本文学にみられる無常観においては、“消滅”はあくまでも“消滅”であって、その視点からのみ無常観は展開してきました。ところが、ここにいたって、“消滅”を“生成”の側面からとらえ直すという新しい視点が提示されたわけで、このことは、無常観の展開史の上でも画期的なことなのです。日本文学の世界では、本来、「生成」と「消滅」との両側面を有する「無常」に対して、早くから「生成」面を捨象し、「消滅」面のみに視点をあてる無常観が展開し、「無常」は「滅び」の原理と認定されてきたという歴史を背負っているのですが、ここにいたって、「無常」を「生成」の視点でとらえようという見方が示されたわけで、これは、まさに注目すべき思想的展開であります。 |
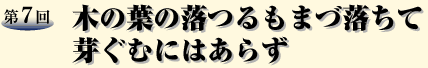
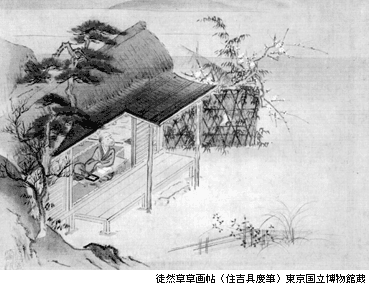 『徒然草』第一五五段には、兼好法師の無常観に基づいた、注目すべきものの考え方があらわれています。第一節では、まず人間のこの世における処世訓として、時機の是非・適否を見きわめることの重要さを説き、続いて、「生・住・異・滅」<仏教で四相という>と変遷する現世における、人間の生・老・病・死<四苦という>の移り変わりは、時機を待たず、瞬時も止(とど)まらないことを述べます。第二節においては、自然界における四季の推移について観察をめぐらし、第三節に及んで、一定の順序に従う自然界の季節の推移に対し、人間における生・老・病・死という変化は、順序を待たず、速やかに不意に来るものであることを説きます。
『徒然草』第一五五段には、兼好法師の無常観に基づいた、注目すべきものの考え方があらわれています。第一節では、まず人間のこの世における処世訓として、時機の是非・適否を見きわめることの重要さを説き、続いて、「生・住・異・滅」<仏教で四相という>と変遷する現世における、人間の生・老・病・死<四苦という>の移り変わりは、時機を待たず、瞬時も止(とど)まらないことを述べます。第二節においては、自然界における四季の推移について観察をめぐらし、第三節に及んで、一定の順序に従う自然界の季節の推移に対し、人間における生・老・病・死という変化は、順序を待たず、速やかに不意に来るものであることを説きます。